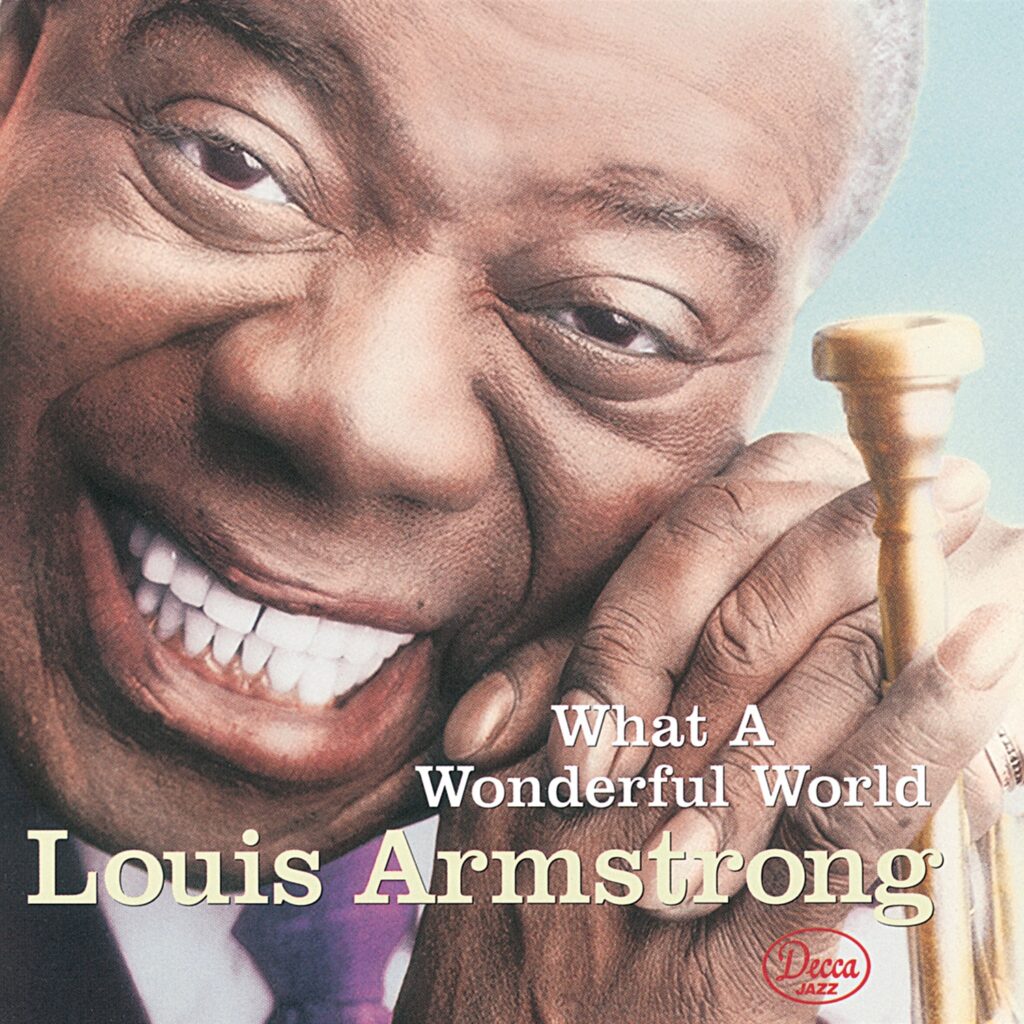「ダニーボーイ」は、アイルランドで歌い継がれてきた民謡に歌詞を付けたものです。今では様々な歌詞も存在していますが、アイルランドの独立運動のために闘いに行ってしまった息子を悲しむものがよく知られています。
日本語でもいくつかの歌詞があります。中でもなかにし礼さんが手掛けた歌詞からは、戦争体験者としてのメッセージを受け取ることができます。
ところが、今日もまたウクライナ情勢は激しさを増しています。
富や利益だけを追求した人間の愚かな醜態が映し出されています。
幸せな暮らしを、争いで勝ち取ろうと勘違いしているかのようです。
たしかに、ぼくも、あれ程酷くはないにしても、調子にのっていました。もっと便利に、もっと贅沢に、もっと儲かるように、そんなことばかりに目を奪われていました。
そうなのです、肝心な暮らしには手に余るものばかりに目を奪われていたのです。
でも、要らぬ思いは降ろします。
ただし、「NO」と伝える意志は持っていようと思っています。
政治家じゃなくても、有名じゃなくても、「STOP THE WAR 」と伝えます。
穏やかな暮らしの中にこそ、幸せはあると気がついているからです。
*ユニセフのウクライナ緊急募金サイトも紹介させてください。