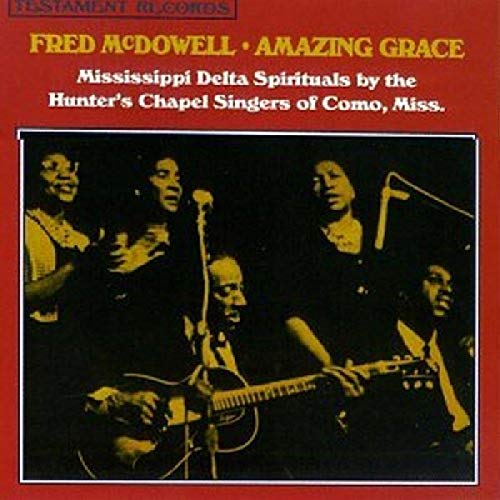心理学用語に「ファイト・オア・フライト」というものがあって、動物はストレスや苦悩に直面すると、その問題に”挑戦”するか、”逃げる”という行動をとると言われている。さらに最近ではその前後に“凍結“と“放棄“も加えられて説明されている。想定などしていない状況では、”凍結(フリーズ)”してしまうし、戦うことも逃げることもできなければ、”放棄(フォーフィット)”してしまうのだということだった。
なるほど上手く説明するものだと理解もしたが、どうしても気になってくるのは今回のコロナ感染のようなケースだ。経験した人は殆どいない状況で、どうやって幸福感を得ていけば良いものなのかと悩みもする。まして今の自分を俯瞰してみれば、”凍結”し閉じ込められている状況で、ただ春が来ないかと願っているだけのようだ。なんだか落ち込みそうにもなってもくるが、それでも昔のブルースマンたちもそうだったに違いないと慰めておきたい。逃げ足の早い奴らが多かったというイメージが浮かぶものの、「どうにもならん」と”放棄”し、酒を呑んでいた輩もたくさんいたはずなのだ。しかもそれでいて、けっこうな幸せも感じ取れていたようにも思えてくる。ロッキン・チェアに居座ってブルースを歌い、酒を浴びることも、時には必要になってくるものなのだ。

さて、今回のブルースマンはハウリン・ウルフ。歴代の中でもイチバン強そうなルックスと名前を持っている。なにせ「吠えるオオカミ」だ。弱いはずがない。声もダミ声で、弱音を吐いたとしても相手にはケンカ腰に届いていたことだろう。ただそんな彼だが、1962年の2ndアルバム「ハウリン・ウルフ」に収録された「Down In The Bottom」では、命からがら”逃走”する歌を歌っている。「ふもとで会おうぜ、俺の靴を持って来てくれ」と始まり「彼女のひどい親に殺されるには若すぎるんだ」と叫んでいるのだ。
1910年にミシシッピ州で生まれたウルフは、チャーリー・パットンにギターの手ほどきを受け、サニー・ボーイ・ウィリアムソンからハーモニカを学んだというから、音楽を学ぶには恵まれていた環境のようだ。それでも抑圧された南部での生活では不平等に扱われたという憤りを抱えていた農夫のひとりであり、40歳でミュージシャンになるまでの楽しみは、仲間内で分かり合える音楽だけのようだった。ブルースが生まれた理由をここで深読みするならば「Down In The Bottom」は、駆け落ちするような悲恋の歌ではなくて、ひどい状況からの脱出の思いが込められていたとも言える。さらに1951年のデビュー・シングル「HOW MANY MORE YEARS」と「真夜中のモーニン」のカップリングでは「どれだけオマエにつきまとわれてきただろう」そして「誰かがドアをノックしている」と歌っている。女とのトラブルを嘆いているようでもあるが、何かに怯えているようでもあり、深い闇に付き纏われているようでもある。
後にシカゴ・ブルースの重要人物となっていくウルフだが、同じく重鎮であるマディ・ウォーターズに比べると、白人の前にはなかなか姿を現すことがなかったようだ。彼にとってのブルースとは、仲間内だけこそが理解してくれるものであり、ゲットー・バーと呼ばれる貧困層に属するアフリカ系アメリカ人が集う場所で歌うものだったらしい。薄汚れたバーで、酒と煙草が染み付いたブルースを歌い続けようとしたハウリン・ウルフは、心臓発作を起こしても医師の指示に逆らい、死の直前まで歌い続けたという。いったい最後はどんな闇に向かって吠えたのだろう。
ところで、オオカミの遠吠えには3つの理由があるらしい。1つめは他の個体に自分の縄張りを知らせ、近づかないようにさせるため。2つめは群れからはぐれた時に仲間を見つけるため。3つめは、仲間との絆を維持するという目的だ。これを知った時、オオカミに備わっている優しさに気がつき驚いた。そして偶然だとしても、ハウリン・ウルフの咆哮のブルースにも、同じ役割が含まれていたように思えてきてならないでいるのだ。