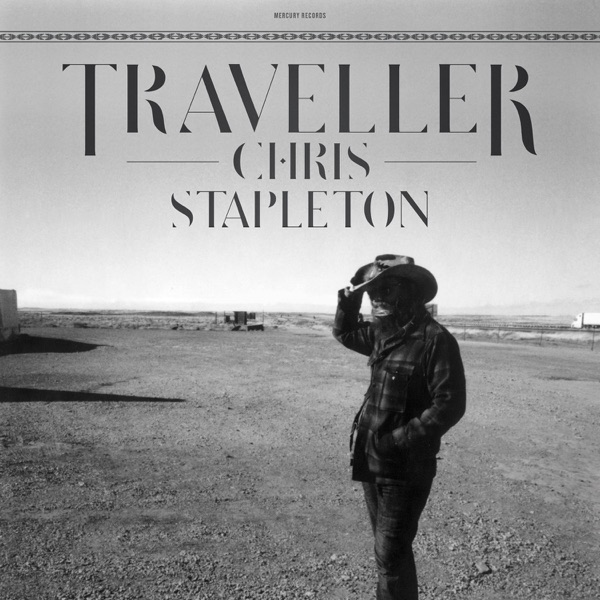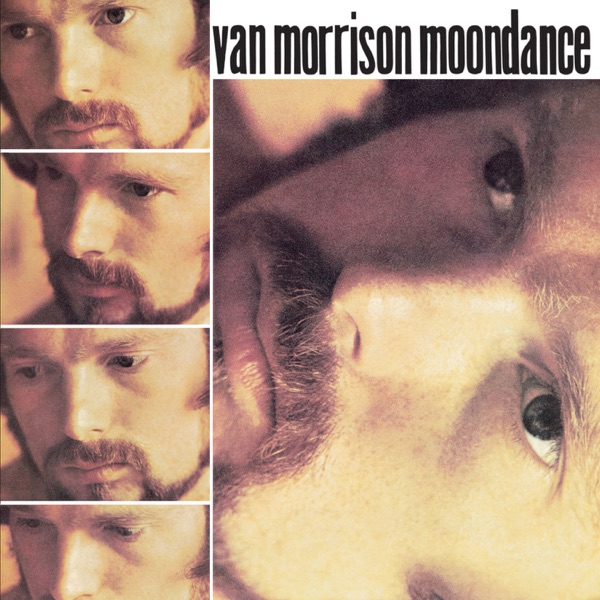ノラ・ジョーンズの来日公演があることを知ったのは8月に入ったばかりの休日だった。よく利用しているコンビニの駐車場にいつのものように車を停めると、彼女の仙台公演を知らせるポスターが目に入ってきた。自画自賛しているつもりもないけれど、その後のチケットを確保する行動は早かった。すぐさま妻に連絡して一緒に行くかと尋ねている自分がいた。だって、あのノラ・ジョーンズが近くに来てくれるんだもの!そりゃー会いに行くしかないでしょう。

そうそう、ノラを本当に好きなった瞬間は今でもハッキリと覚えている。それは思春期の真ん中にいた頃の長男と2人でドライブに出かけた時のことだった。その頃の僕はとても疲れていた。いや、自分の人生を嘆いていた時期だったと言う方が正しいのかもしれない。職場でも家庭でも、とにかく全てのことに対してイライラしていた。この文章を書いている途中で思い返してみても、灰色の雲が広がり迫ってくるようで苦しくなってしまう。そんな心模様の中で聴いた音楽がノラ・ジョーンズだったのだ。
「なんか、こういう音楽はいいよね?」「癒されない?」彼女の1stアルバム「Come Away With Me」を車の中で聴きながら、そんな風に僕は息子に尋ねていた。
「ふーん、そうだね…」彼は彼なりに気を遣ってくれていたと思うのだが、それでも優しい眼差しを返してくれたことが嬉しかった。
「こう言うJAZZ?っていいんだな…」JAZZがどのようなものなのかさえ分かっていなかった僕は、こうしてノラ・ジョーンズという特殊なJAZZにハマっていったのだ。
さてさて、2022年のノラ・ジョーンズの仙台公演だが、当日券も発売されていたりと、客足もまばらなのかと思ってはいたのだが、会場のゼビオ・アリーナはほぼ満杯だったと思う。客層はひとりで見に来ているらしい30代から40代の女性客と、ご夫婦のようなカップルが目立ってはいたが、その中に混じって年配の方々も多く見受けられた。皆さんとてもお洒落していて、この日を楽しみにしている様子が伝わってくる。
オープニング・アクトはロドリゴ・アマランテ。ブラジルはリオデジャネイロ出身のシンガー・ソングライターだ。ノラとは以前に2曲をコラボし配信リリースもしている。この日はギターとピアノでブラジル音楽を堪能させてくれた。予備知識がまったくなく初めて聴いたのだが、好みの曲が数曲あって現在チェック中のアーティストだ。さて、彼のステージが終わり、15分ほどの休憩を挟んだ後にいよいよノラが姿を現した。
オープニング・ソングは「ジャスト・ア・リトル・ビット」だ。会場の照明が落ちると、バンドのメンバー3人がステージに登場し、イントロが流れ出すとノラがステージに現れた。彼女は中央に置かれたスタンドマイクの前で両手を高く上げると、そのまま揺らしながら歌い始めた。ピアノを弾かずに立って歌うノラは幻想的で美しく、そしてたくましくさえ感じた。彼女特有の可愛らしさは残っているのだが、力強さもみなぎっているようだ。パンデミック以降はライブどころかセッションもままならないでいたと言っていたから、それらを乗り越えてステージに立てる喜びを表現してくれたのかもしれない。

この日のセットリストはこれまでのノラの歴史を辿るかのように多くのアルバムから満遍なく披露されていたようだが、デビュー作「COME AWAY WITH ME」の20周年盤のリリースに合わせて、このアルバからは多くの曲を披露してくれた。そしてそれらの全てに新しいアレンジが施されているのがスリリングだった。歌い回しにしてもどんな風に歌ってくれるのかと最後までドキドキさせてくれる。それでも終わってみれば幸福感という余韻に浸れるのだからお見事という拍手が会場を包んでいく。何度も聞いていきた「Don’t Know Why」も本編の最後で聞くことができた。とりわけ大きな拍手で迎えられたこの曲は、いつもよりゆっくりな歌い出しから始まり、絶妙なノラのタメが僕たちを魅了した。本当に素敵なコンサートだった。
日本ツアーの前に行われたアメリカ・ツアーの様子などを見てみると、観客の声援も大きくて既にコロナは昔の出来事のように感じさせられる。しかし、日本では未だに規制もあったり、ひとりひとりが抑制をしているので歓声などは少なかった。ただ、盛り上がっていなかったわけでないとノラや演奏してくれたメンバーに伝えたい。あそこの会場にいた誰もが心の中で「ありがとう」を連発していたと思うから。そうそう、ノラの日本語「アリガトウ」はものすごく上手だった。そこも嬉しかったな。ノラ・ジョーンズ、素敵な女性でした。