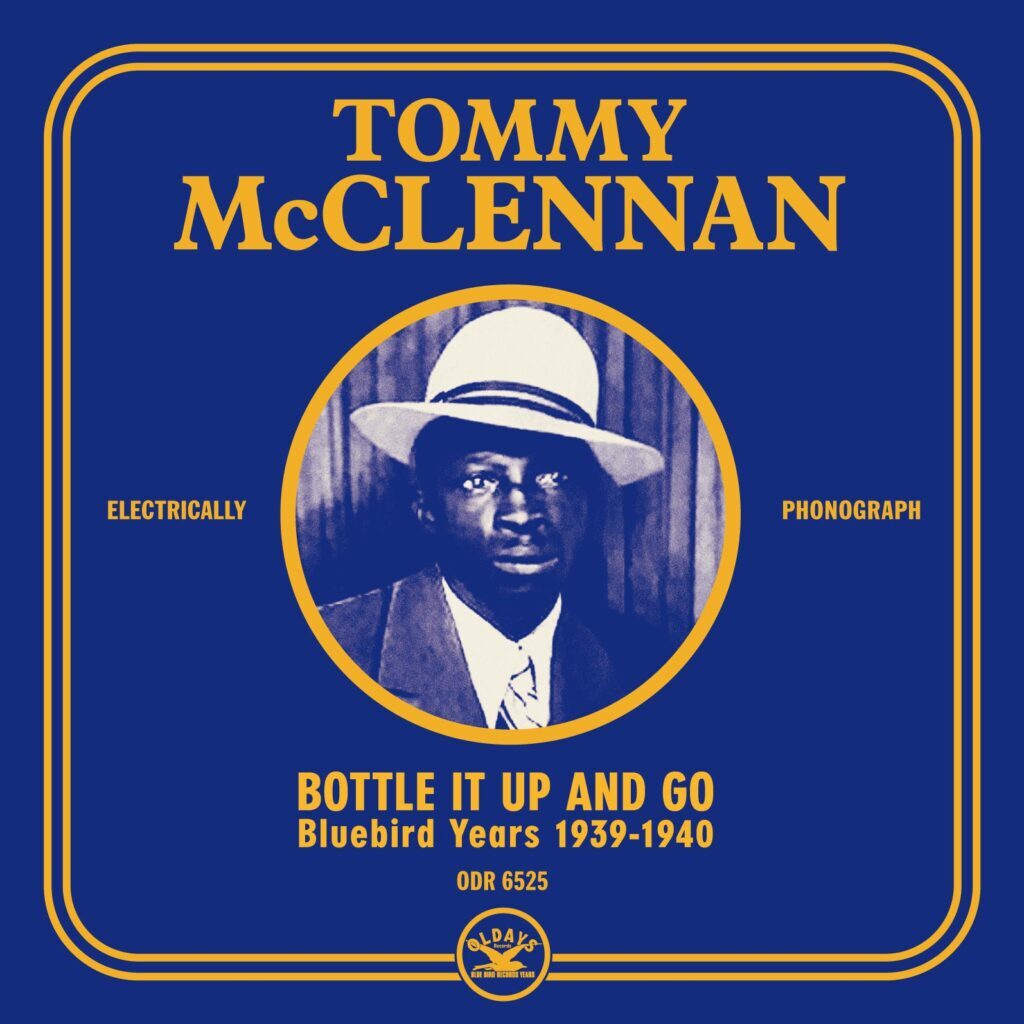何にも束縛されずに自由でいたい。そんな風に思っている人はたくさんいるだろう。でも「自由とは何か」の問いに明確な答えを出せる人はいるだろうか。たとえ社会生活を捨てて生きれたとしても、この地球上に存在する以上は何かしらのルールに縛られてしまう。自由への憧れは、ぼんやりとしたままで終わるものなのかもしれない。それでもその答えに対して明確に答えた女性シンガーが存在していた。彼女の名前はニーナ・シモン。彼女の真実に迫るドキュメンタリー映画「ニーナ・シモン〜魂の歌」を見たことがある方なら、映し出されたニーナの印象的な答えを既に見つけていることだろう。そして「自由になりたい」という邦題がついた「I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free」の歌に癒されていたはずだ。

さて、ニーナ・シモンは、1933年、ノースカロライナ州のトライロンに7人兄弟の6番目として生まれた。貧しいながらも熱心なクリスチャンの家庭では賛美歌を歌うためにピアノによる音楽があふれていた。そんな環境でニーナは幼い頃からピアノを弾き始め、その才能を見出されていく。周りからの支援も受けるようになると、黒人女性初のクラシック・ピアニストになるべくジュリアード音楽院に進学するまでに成長した。しかし、黒人であることの差別はまだ激しく、クラシック・ピアニストへの夢はそこで閉ざされてしまった。それでもニーナは家族を助けるため、ナイト・クラブでピアノを弾き始める。さらにそこではオーナーの強い要望と週給90ドルを断れずに、嫌々ながらだが歌うことも始めた。ところがそのおかげで彼女は人気者になり、レコード・デビューのチャンスが舞い込んでくる。1957年には「I Love You Porgy」がヒット。その後はライブ・アルバムも多く発表し、そのコンサートの様子が各方面で喝采を浴び、スターへの扉が開かれていくのだ。マスコミはニーナを取り上げ、コンサートの依頼は殺到した。クラシック・ピアノの技術にナイト・クラブで得たジャズの要素を取り込んだ演奏は独自のもので、彼女への関心は広がるばかりだった。
ニーナは今まで見たこともない金額の小切手を受け取り、コンサートの収入も増え続けた。大きいクローゼットにゆったりしたバスルーム。最新のベンツも手に入れた。そして後に夫でマネージャーとなるアンドリューと出会う。人生の幸福感は、お金や名誉だけでは測れるものではないが、彼女にとって最初の到達点だっただろう。まもなく二人の間には娘も生まれ本当に最高潮な生活だった。夫のアンドリューのマネージメント能力は高く、仕事もどんどん忙しくなっていった。しかしそんな中、アラバマ州にあるバーミンガムの黒人教会で爆破事件が起こる。KKKという白人至上主義者の団体が爆破させたのだ。11才と13才の少女4人が殺されてしまう。ニーナは怒り狂ったように「Mississippi Goddam」という曲を作り、当時盛り上がりつつあった公民権運動へ傾倒していく。「この国はどこも嘘だらけ」「私たち黒人は立ち上がる時が来た」と、痛烈な人種問題への警告を放ったのだ。
こうして黒人のために戦う歌手へと変貌していったニーナは、次々と政治的に過激な歌を歌っていくようになった。ついにはキング牧師ら指導者たちとも出会い、その活動もより活発になっていく。「この白人たちと戦う準備は出来たの?」と歌った「Are you ready BLACK PEOPLE」のライブ映像などを見ると、公民権運動の中心にいたことは明らかだ。だが、そのことで彼女は音楽のメインストリームからは外されてしまう。あまりにも強烈な歌をどんどん作っていくことで放送禁止になる曲も出たりと、収入の面でも落ち込んでいくのだった。さらに私生活の方でも、マネージャーでもある夫との揉め事が多くなり、暴力沙汰も増え、やがてDV依存症にまでなってしまう。
それでも貧しさから抜け出せた時のように彼女には音楽が残っていた。どうやら自由の姿を見出したのはこの頃のようだ。どんどん精神状態が追い詰められていく中で登ったステージの上で、彼女は何度かその自由を感じたことがあるというインタビューを残している。それはこんな言葉だ。
「自由とは、恐れのないこと」
凄い言葉は頭で理解してしまう前に感じてしまうものだが、この言葉に触れた時も同じことを感じてしまった。偉大なアーティストたちは、自分の苦悩を作品に込めて昇華させることで危うい精神状態を開放し、自由を得ていると聞いたことがある。どうやらニーナもそのようだ。そして冒頭で紹介した「I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free」だが、この曲は1963年にビリー・テイラーが書いた曲で、後に「自由な気持ちを知ることができたらいいのに」という歌い出しから始まる歌詞が付けられたもの。それをニーナが1967年にカバーしている。彼女のファンには人種間の問題や、ジェンダー問題のような複雑な問題を抱えている人たちが多いという意見を目にするが、結局はどんな人も複雑に生きているのだと思う。何かを失ったり、失敗したり、希望を持てなくなったりと、そんなことを毎日繰り返しているからだ。だから、たとえ彼女の熱烈なファンではなかったとしても、自分の味方のように鼓舞してくれるニーナの歌声は聴いてみてほしいと思っている。