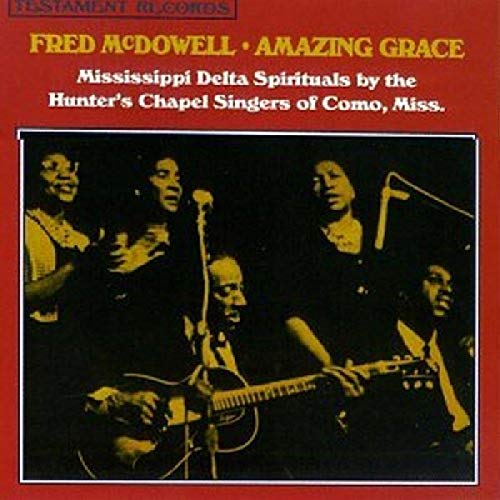地方の小さな町に店を開いて20数年が経つが、同じ商店街の方々が続けてお亡くなりになる経験をしたのは初めてのことだった。ずいぶんと寂しくなってきた商店街だが、これでまた店舗の数が減ってしまうことになる。駅前に百貨店があって賑わっていた頃が懐かしい。お亡くなりになられた方々は、昭和の時代から店を切り盛りされていた店主の方々が多く、皆さん最後まで店に立たれていた。それぞれの持病に悩まされていたらしいのだが、そんな素振りも見せてはいなかった。「あそこの店に行くのが楽しみだった」そんな言葉もたくさん届いているし、自分もそのひとりだった。こんなことになるのならば、もっとありがとうを伝えておけばよかった。こういう時はいつも心に残ってしまうが、自分にできることは多くはない。どうぞ安らかにと祈らせて頂くことぐらいだ。

さて、あたりまえと後悔はいつも背中合わせなものだが、ゲイリー・デイヴィスは「Death Don’t Have No Mercy」でそれを見事に表現している。牧師でもあった彼だけに、「死は誰にもやってくるものだから、後悔のないように生きなさい」と説法をしているのだ。さらに残されていた映像を見てみると、誰かが亡くなったことを悲しく思っている気持ちも表していたことに気がついた。きっと色々な解釈があっていいのだろう。ブルースの正解もひとつじゃないのだ。矛盾さえも赦してくれている存在、現象を超えて在るもの。ゲイリー・ディビスの声にはそんな”何か”が含まれていると思う。
Death Don't Have No Mercy Rev.Gary Davis 死神はこの世で情け容赦などしない 死神はこの世で情け容赦などしない 奴はあんたの家にも訪れ、そしてさっさといなくなる ベッドに目を向ければ、きっと誰かがいなくなっている筈さ 死神はこの世で情け容赦などしない そうさ、死神はこの世の全ての家族のもとに行く そうさ、死神はこの世の全ての家族のもとに行く そうさ、奴はあんたの家にも訪れ、そしてさっさといなくなる そうさ、ベッドに目を向ければ、あんたの家族の一人がいなくなっているだろう 死神はこの世の全ての家族のもとに行く そうさ、死神はこの世では休暇はとらないからな そうさ、死神はこの世では休暇はとらないからな そうさ、奴はあんたの家にも訪れ、そしてさっさといなくなる そうさ、ベッドに目を向ければ、最愛の母親がいなくなっているだろう 死神はこの世では休暇はとらないからな
5歳の頃からハーモニカを吹きはじめ、続いてバンジョーとギターを手にしたゲイリー・デイヴィスは、7歳の時にはもうギターを弾く仕事につき、14歳の時にはストリング・バンドを結成して各地を演奏してまわっていた。まさに天才肌だったとしか言いようがない。ところがその時期に彼は失明をし、その事件をきっかけに信仰に傾いていくこととなる。1933年にノースカロライナ州のワシントンで牧師に任命された彼は、1935年にブラインド・ボーイ・フラーと最初の吹き込みもしているが、ブルースの曲は少なく、もっぱら宗教的なものだったらしい。その後は「聖なるブルース」とも呼ばれていくのだが、内容的には純然たるゴスペル・ソングだけを歌いとおした人生のようだ。
失明という事件は、昨日までの”ふつう”が、今日になって”特別”なものだったと知るには十分すぎるものだったことだろう。学校や仕事、人間関係、病気と、誰の人生にも四苦八苦はつきまとうが、それらには押し潰れそうな痛みを取り払うチャンスは残っている。光を見ることができなくなったゲイリー・デイヴィスは、いったい何を見ようとしたのだろう。そして何を伝えようとしたのだろう。想像を張り巡らしてはみているが、けっきょく答えなどは出やしない。
ただ最後にエピソードをひとつ紹介したいと思う。自分の店では幅広い年代のお客さまがいらっしゃるので、BGMは聴きやすいボサノバやポップスなどを選んで流している。ただし数曲だけはブルースを仕込んでいて、それが流れた出した時には、こっそりとほくそ笑んでいたりもするのだ。今日はショートカットの女性を接客中に、偶然にも「Death Don’t Have No Mercy」流れ出した。するとその女性は「この曲カッコイイね、ブルースっていうの?」「うねり?みたいなのが素敵ね」と言ってくれた。盲目のシンガーで牧師さんなんだよと伝えた後で、死神の歌だってことは黙っておいた。歌詞も大事だろうが、静かに流れてきた音だけで癒されてくれたのだ。なんだか「それでいい」と、ゲイリー・デイヴィスも言ってくれたような気がした。今度また彼女が来た時には、別の曲も聴かせてみたいと企んでいる。