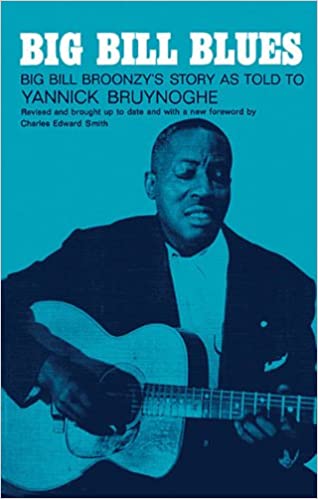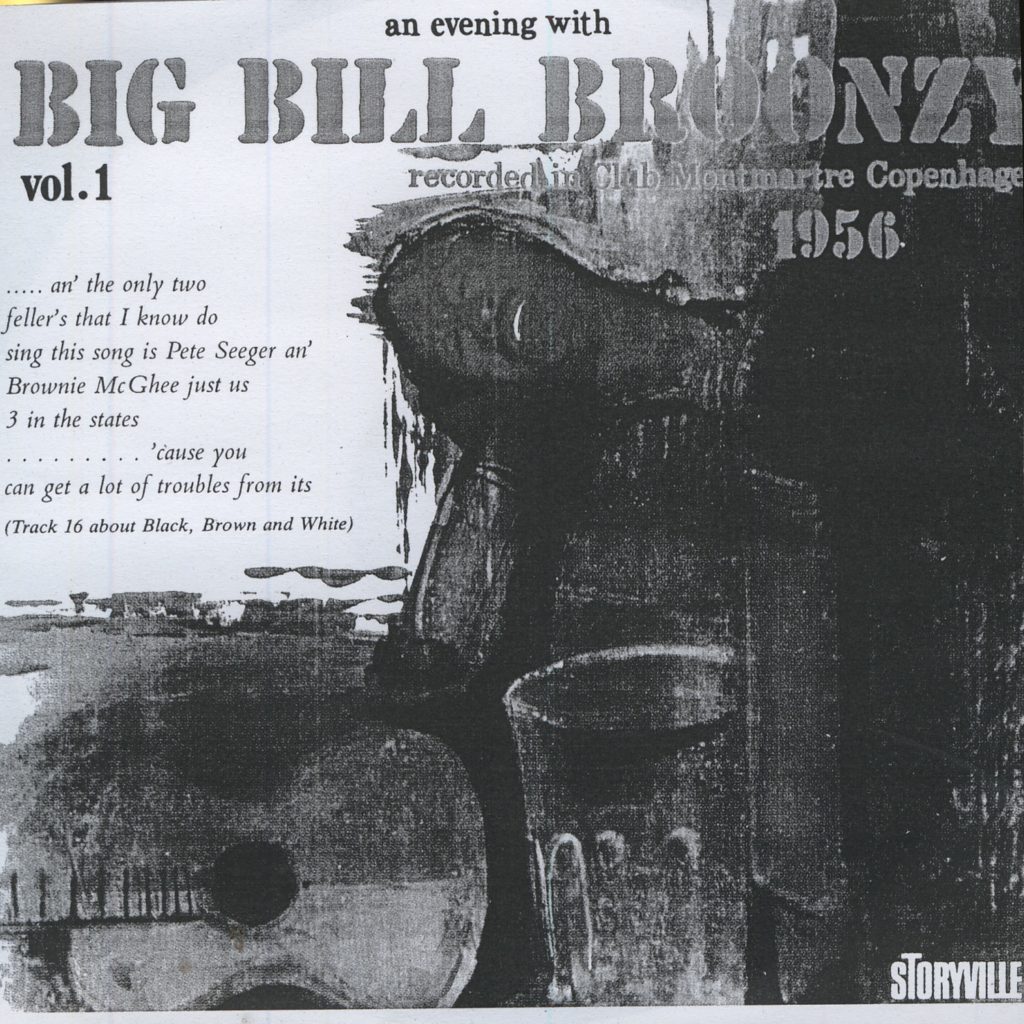ブルースには様々な演奏スタイルがあるが、ギターに関してもチューニングを変えてみたり、酒の瓶やナイフで弦をスライドさせてみたりと、斬新なテクニックや奏法も生まれてきた。近年においてもそれらを受け継いでいるアーティストは多く、ブルースだけでなくコンテンポラリーな音楽でも耳にすることができる。1900年代初頭まで、アメリカ南部の黒人たちの憩いの場はジューク・ジョイントと呼ばれる酒場だった。農園などで働く彼らの楽しみといえば、そこに集まりミュージシャンの演奏に合わせてダンスすること。そして既にこの頃からギタリストたちは酒場にあった身近な道具を巧みに使い、スライド奏法を披露し客を盛り上げていたという。最初にスライド・ギターが録音されたブルース・レコードは1923年のシルベスター・ウィーバーの「Guitar Blues」で、当時の情景が浮かび上がるインストルメンタルの曲だ。さらに1940年代後半に進むと、低所得者だった黒人層をターゲットとしたブルースのレコードも数多く発売されるようになり、スライド・ギターの名手と呼ばれる男たちも次々と登場してくるのである。エレクトリックによるスライドでシカゴを震わせたマディ・ウォーターズ。チェス・レコーズにマディと同じく在籍したロバート・ナイトホーク。そしてキング・オブ・スライド・ギターといえばエルモア・ジェームスだ。真っ先に浮かぶ「Dust My Broom」に代表されるように、あのエルモア節はスライド・ギターの枠を超えてブルースのスタンダードとなっていく。

さて、その王様であるエルモアが憧れていた男がタンパ・レッドだ。1928年「It’s Tight Like That」で「あの娘はキツイ」とふざけた歌を歌い、それが当たったことでシカゴに住みつき、アル・カポネにも贔屓にされながら1950年代まで大量のレコーディングを続けていく。見事なスライド・ギターの腕前から「ギターの魔術師」とまで呼ばれ、陽気なラグタイムやホウカム・ソング、沈着なスロー・ブルースまでそのレパートリーは広かった。
生涯で300曲以上の録音をこなした彼だが、歌詞を見ても優れたものが多く「Kingfish Blues」では自分を魚の王様に、女たちを小魚に例えて「タンパ・レッドはどんな小魚を選んだら良いか知っているぜ」とも歌い上げている。ギャングスターにも贔屓にされていたくらいなのだから、なかなかの気骨も持ち合わせていたのかもしれない。けれども、「お前が愛してる男はお前を傷つける」「お前が不幸になることに俺は心を痛めてる」と歌う彼の代表曲「It Hurts Me Too」を聴くと、実際のところはこのブルースマンにしても、見栄を張り続けた大ボラ吹きだったのかもしれないとも思えてくる。
ところで肝心のスライド奏法だが、タンパ・レッドは単弦でのスライド奏法を確立した最初の人物である。そしてその奏法は戦後のロック・ギターにおけるチョーキングなど、スクイーズ・スタイルにまで影響を及ぼしている。ここはものすごく重要だ。彼のスライドは、フレーズの最後を細かく揺らしてビブラートをかけていることが多い。それに憧れたB.Bキングやバディ・ガイは、自身もスライドを試してみるのだが上手くいかず、その代わりにチョーキングで表現することに決めたという。そしてそれがブルーノートと呼ばれるジャズやブルースで使われる音を表現するのにピタリとハマっていくのだった。繊細な音使いのタンパ・レッドがいたからこそ、次の世代がまたイキイキと表現できたのだ。
さてさて、「It Hurts Me Too」をカバーしてもっとも有名にさせたのは、エルモア・ジェームスだ。リズムをスローにして、出だしからエルモア節で泣いている。同じようなブルースを体験し、タンパ・レッドを聴いて泣いていたのだろうか。オリジナルよりもブルースにどっぷり浸っている。寂しさを振り払うように練習していたのかもしれない。ギターを弾いていた部屋には、酒の空いたボトルがそこら中に転がっていそうだ。だからなのだろうか、スライド・ギターは咽び泣いている男の声にも聞こえてくるのだ。